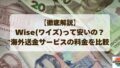こんにちは、カリママです。
久しぶりの日本、実家での穏やかな時間。 その静寂は、母のふとした一言で破られました。
「ねぇ、このフィリピンのニュース、見た?」
差し出されたスマホの画面には「ゴミ山崩落、死傷者多数」という痛ましい文字が並んでいました。
「えっ…」
多くの人にとって、このニュースは「遠い国の、可哀想な出来事」かもしれません。
でも、私がその記事を目にした瞬間、学生時代に肌で感じたあの「熱気」と、鼻をつく強烈な「発酵臭」が鮮烈に蘇ってきたのです。
今日は、いつものアメリカ生活ブログとは少し趣向を変えて。
フィリピンで見た過酷なゴミ山の記憶と、そこで出会った家族の話。
そして、アメリカで暮らす私の友人の「強さ」にも通じる、私たちが忘れてはいけない「生きること」について綴りたいと思います。
2026年1月セブ島ゴミ山崩落事故のニュースと共に蘇った記憶
母と向かい合い、他愛もない話をしながら箸を動かす時間。
アメリカで無意識に張っていた気が緩み、やっぱり実家が一番落ち着く場所だと心底感じていた、その時でした。
「そういえばあんた、学生の頃フィリピンのゴミ山に行ってたよね?」
母は箸を止めることなく、まるで明日の天気の話題でもするかのような何気ない口調で続けました。
「このニュース、見た? ゴミ山が崩れたって」
差し出されたスマートフォンの画面。
(出典)読売新聞:フィリピン・セブの廃棄物の山崩落事故、36人死亡…行方不明者の捜索終わる
そこには、今まさに私たちが食べている温かい食事とは対極にある、冷酷な現実が映し出されていました。
口の中に入れていたご飯の味が、一瞬でしなくなりました。
画面の中の「死傷者多数」という文字を見た瞬間、目の前の景色が歪み、当時の記憶が溢れ出してきたのです。
私が学生時代に足を踏み入れた場所とは違う、セブ島の現場。
けれど、写真から伝わってくる空気感は同じでした。
鼻をつく腐敗臭、湿った熱気、そして生活のすべてがゴミと共に回っている場所。
平和な食卓で箸を握る私の手と、その画面の向こうにある現実。
そのあまりの落差に、私は言葉を失い、ただ呆然と画面を見つめることしかできませんでした。
映画『Crazy Beautiful You』に導かれ、私が「パヤタス」へ向かった理由
時計の針を、私がまだ学生だった頃へと戻します。
当時の私は、ある一本のフィリピン映画に心を奪われていました。
フィリピン女優であるキャスリン・ベルナルド主演の『Crazy Beautiful You』
スクリーンの中で描かれる、医療ボランティアや現地の人々との交流。
そこで描かれる人間ドラマは、平和な日本でぬくぬくと育った私にとって、あまりに鮮烈で、眩しい世界でした。
「映画の中の景色を、この目で見てみたい」 「私にも何かできることがあるんじゃないか」
そんな衝動に突き動かされるようにして、私はボランティア活動に参加し、フィリピンのマニラへと飛びました。
映画の雰囲気を知りたい方はこちら:
(YouTubeが開きます)
そして、現地の現実を肌で感じるために向かったのが、かつて第二のスモーキーマウンテンと呼ばれた場所「パヤタス」でした。
車を降りた瞬間、まず私を襲ったのは「匂い」です。
鼻の奥にこびりつくような、生ゴミが発酵した強烈な臭気。
そして目の前にそびえ立つのは、巨大な山。
でもそれは土や岩ではなく、すべてが人々の生活から出た「ゴミ」でできた山だったのです。
(※以下、私が実際に当時現地パヤタスで撮影した写真です)

その山の麓に、ひっそりと佇む石碑がありました。
2000年7月、降り続いた雨によってゴミ山が崩落し、数百人もの命が奪われた大事故。
その犠牲者を弔う慰霊碑です。

私はその前で手を合わせました。
映画で見た美しいストーリーとは違う、厳しく、重たい現実。
ニュースで見た「崩落」という言葉が、ここでは過去の痛みとして、静かにそこに在りました。
補足:
パヤタスの歴史や過去の崩落事故について、客観的なデータや詳細をもっと知りたい方は Wikipedia(パヤタス・ダンプサイト) もあわせてご覧ください。
「ご飯はジョリビーの食べ残し」ゴミ山の麓で出会った家族が語ったこと
そんな山の麓で暮らす、ある家族に話を聞かせてもらいました。
私がどうしても知りたかったのは、この過酷な環境での「家族の在り方」でした。
彼らの住居は、廃材を組み合わせて作られた小さな小屋。
広さは、日本にある多目的トイレと同じくらいだったでしょうか。
畳で言えば、2枚あるかないか。
そんな大人が手足を伸ばして寝るのもやっとの狭い空間に、家族四人が身を寄せ合って暮らしていたのです。
マニラの湿った熱気がこもる室内、エアコンなんてありません。
テレビもなければ、家具らしい家具もない。
ただ、家族がそこにいるだけの空間。
「普段、ご飯は何を食べているの?」
恐る恐る尋ねた私に、彼らは隠す様子もなく、あっけらかんと答えました。
「ゴミの中から拾ってきた、ジョリビーの食べ残しだよ」
ジョリビーとは、フィリピンで国民的な人気を誇るファストフード店のこと。
彼らは捨てられたチキンなどを拾い集め、それを洗い、再び火を通して皆で分け合って食べていたのです。
日本の多目的トイレほどの広さ、灼熱の部屋、そして残飯の食事。
日本から来た私にとって、それは想像を絶する「極貧」の光景でした。
けれど、私の心を何よりも大きく揺さぶったのは、その話をしている時の彼らの表情でした。
悲壮感なんて、微塵もなかったのです。
狭い部屋だからこそ、彼らは常に肩を触れ合わせ、互いの体温を感じていました。
彼らは本当に愛おしそうにお互いを見つめ、笑っていました。
「家族みんなが一緒にいられるから、幸せだよ」
その言葉を聞いた瞬間、私は衝撃を受けました。
モノがなくても、家が狭くても、食べるものが拾ったものであっても。
「家族がいる」ということに、彼らは心からの幸せを感じていたのです。
私がそれまで信じていた「幸せ」や「豊かさ」の定義が、ガラガラと崩れ落ちたのを覚えています。
そして、家のすぐ裏には、いつ崩れてくるかわからない巨大なゴミの山があるという現実。
窓のない部屋には、常に生ゴミの発酵した臭いが充満しています。
2000年に起きたあの大規模な崩落事故で大勢の命が失われたことも忘れてはいないはず。
「怖くないの? 他の場所に引っ越そうとは思わないの?」
私の問いかけに、お父さんは少しきょとんとして、そして穏やかにこう答えました。
「どうして? ここは私たちの家だから」
雨風をしのげる屋根があり、家族みんなが肩を寄せ合って眠れる場所。
今日食べるご飯があり、子供たちの笑い声がある場所。
彼らにとっての「家」とは、安全な土地や立派な建物のことではなく、「家族が一緒にいられる場所」そのものを指していたのでした。
当時、日本で「安全」が当たり前の生活をしている私が、勝手に「可哀想」という物差しで彼らを見ていたことに気づかされ、恥ずかしくて胸が熱くなりました。
アメリカ生活で感じるフィリピン人友人の「強さ」の正体
あれから長い時が経ち、今、私はアメリカで暮らしています。
ここにも、私の大切なフィリピン人の友人たちがいます。
先日、フィリピン人のママ友のバースデーパーティーに招かれた時のことです。
ズラーっと手料理が並んでいました。
甘辛いアドボの香り、鮮やかなパンシット、そして私の大好物である揚げ春巻き「ルンピア」。
「ちゃんと食べてる?たくさん食べてね!」 「持ち帰り用の容器もあるからね!」
彼女たちは常に周りを気遣い、笑い、歌い、そして家族や友人を何よりも大切にします。
その空間で、揚げたてのルンピアを頬張った時、ふと、学生時代のあの記憶が鮮やかに蘇り、1本の線で繋がった気がしました。
パヤタスの狭い小屋で、ジョリビーの残飯を分け合っていたあの家族。
そして今、アメリカという異国の地で、豊かさを分かち合っている彼女と家族。
置かれている環境はまるで違います。
けれど、その根底にある「強さ」は驚くほど同じだったのです。
彼女のあの輝くような笑顔や、他人をも家族のように包み込むホスピタリティ。
それは単なる国民性や性格という言葉で片付けられるものではありませんでした。
もしかしたら、彼女のあの明るさは、過酷な歴史や環境の中で、フィリピンという国の人々が培ってきた「生き抜くための知恵」そのものなのかもしれません。
モノがなくても、家が狭くても、あるいは異国の地で苦労があっても。
「家族がいれば幸せ」「笑っていればなんとかなる」
そうやって命を燃やし、手を取り合ってきた人々の末裔が、今、私の目の前で笑っている彼女の家族なのです。
パヤタスで私が衝撃を受けた「幸せの定義」。
それは幻ではなく、形を変え、場所を変え、ここアメリカで私の友人の笑顔の中にしっかりと息づいていました。
遠い国のニュースを自分事として捉えるとは?
今回のニュースになった場所は、私が学生時代に訪れたパヤタスとは違う、セブ島の埋立地です。
地図で見れば、遠く離れた場所かもしれません。
そして今、私がいる日本の実家からは、さらに遠い海の向こうの出来事です。
けれど、私にはどうしても、これが対岸の火事だとは思えないのです。
スマホの画面に映る無機質な「死者数」や「行方不明者数」という数字。
でも、私には分かります。
その数字の「1」の向こう側には、あのパヤタスの家族のように、狭い家で肩を寄せ合い、ジョリビーの残飯を分け合いながらも「幸せだね」と笑い合っていた、温かい食卓があったはずなのだと。
あの発酵臭のする中で、子供の髪を撫でていたお母さんの手があったはずです。
家族を守るために、ゴミ山で汗を流していたお父さんの背中があったはずです。
もし、あの時出会った家族が、このニュースの当事者だったら。
もし、アメリカで仲良くしてくれているあのママ友の故郷が、ここだったら。
そう想像した瞬間、胸が押し潰されそうになりました。
遠い国のニュースを「自分事」として捉えるということ。
それは、単にニュースを見て「可哀想に」と涙することではない気がします。
そこにあったはずの「暮らし」や「笑顔」、そして必死に生きていた「体温」を想像すること。
見知らぬ誰かの悲しみを、自分の大切な友人の痛みとして感じること。
パヤタスのあの狭い小屋で見た、キラキラした瞳。
アメリカのホームパーティーで見た、弾けるような笑顔。
その2つを知っている私だからこそ、このニュースをただの「情報」として流してしまうことは、どうしてもできなかったのです。
まとめ
日本の実家で母とニュースを見ていたあの瞬間から、私の心はずっと海の向こうにあります。
今回ニュースになった場所で、どれほどの恐怖や悲しみがあったのか。
私には想像することしかできません。
けれど、かつてパヤタスの狭い小屋で見た、あの家族の笑顔を知っているからこそ、失われた命の重みが胸に深く突き刺さります。
私たちが当たり前のように享受している雨風をしのげる家や明日への安心が、実はどれほど奇跡的なことなのか。
そして、どんなに過酷な場所でも、人は手を取り合い、笑い合うことができるほど強い生き物なのだということ。
母との会話と、今回のニュースは、アメリカでの忙しい日々で薄れかけていた大切なことを、私に思い出させてくれました。
遠い空の下から、今回の事故で亡くなられた方々の魂が、安らかであることを心から祈ります。
そして、今もなお不安の中で過ごされている方々に、一日も早く平穏な日々が戻りますように。
遠い過去の記憶と、目の前のニュース。 それを繋いでくれた母との会話に感謝しながら、私はこの記事を書くことができました。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
皆さんの今日が、穏やかで温かいものでありますように。